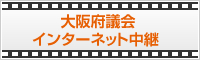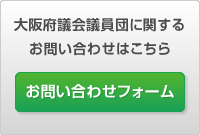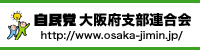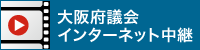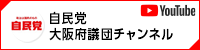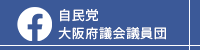平成26年5月定例議会 一般質問
平成26年5月28日
出来 成元 議員
1.枚方市内における支援学校の新規整備について
- Q1)
府教育委員会において、平成21年度に「府立支援学校整備基本方針」を策定され、府内4地域に新たな支援学校を整備されるとともに、うち、3地域に高等支援学校を併設されることになっています。
北河内地域においては、平成27年4月に枚方市立村野中学校跡地に支援学校と高等支援学校を開校するべく、整備中とのことであります。
とりわけ、卒業後の社会的自立に向けた就労支援に取り組む高等支援学校については、企業団地が集積している枚方市の特性を活かし、職場実習の受入れや就労につながるための企業との連携のほか、充実した職業教育が実施されることを期待しているところであり、来年4月の開校は、保護者をはじめ、関係者も心待ちにしていることと思います。
地元住民からは「学校に隣接する市道が狭く、通学バスが十分に出入りできるのか」といったことや、「学校の最寄駅となる村野駅前の府道には歩道がなく、自主通学する生徒が安全に通学できるのか」といった不安の声も出ており、私も、学校を整備することと合わせ、通学の安全確保を図ることは必要不可欠なことだと言ってきました。
特に、村野駅前の府道は、沿道に商店や民家が連なっており、早期に歩道を整備することは困難であることは私も理解していますが、高等支援学校等の生徒にとっては、自力で公共交通機関等を利用し自主通学を行うことは、就労等による社会的自立を実現するための学習活動のひとつであります。その環境整備を行う視点からも、通学路の安全確保は重要であり、これまで府教育委員会として、どのように取り組んでこられたのでしょうか。 - Q2)
地域の小・中学校で、「ともに学び、ともに育つ」教育を推進していくためには、福祉、医療、労働などの関係機関との綿密な連携が必要であり、障がいのある子どもに対する小・中学校の教職員の教育的力量を上げていく必要があると考えます。
そのうえで、専門教育機関としての支援学校の役割に大いに期待しているところであります。
また、来年4月の開校後は、支援学校や高等支援学校も地元に溶け込み、愛される学校になってほしいと私は切に願っており、そのために、地元と多様なつながりを持ち、支援学校の活動内容を理解してもらうことが肝要であると考えています。
これらを実現するために、開校後の具体的な取組みとしてどのようなものを考えているでしょうか。 - 結び)
府教育委員会が設置者として、通学の安全確保のために努力をしていることは理解しますが、学校に通う児童・生徒に事故があってからでは遅く、学校開校後も、更なる安全確保に向けての対策を継続的に検討する様、強く要望しておきます。
また、支援学校に通う子どもたちも、地域の学校に通う子どもたちも、ともによりよい教育環境の下で、健やかに、いきいきと学べるように条件を整え、「ともに学び、ともに育つ」教育を推進していくことは教育委員会の責務と言えます。
よりよい教育環境を整えるにあたっては、地元の皆さんや関係機関との連携は重要であります。
開校後も是非、地元の皆さんの声を真摯に受け止め、開かれた学校運営を行ってもらいたいと思います。
2.大阪市立学校の府への移管について
- Q1,2)
大阪市立の特別支援学校の府移管については、本年1月の時点では、平成27年4月に移管とされていたものが、4月18日に開催された府市統合本部会議において、移管時期を平成28年4月に変更するとの方針が示されましたが、突然1年延期することとした理由は何なのか、きちんと説明をお願いします。
また、先の2月議会において条例提案がなかった時点で、「関係者へのアナウンスは少なくとも1年前には行わなければならない」という昨年の9月議会における中原教育長の答弁を鑑みますと、27年4月の移管は不可能であることが明らかだったのですから、教育長としては、「27年4月の移管はできない」と、はっきり府の見解を言うべきだったのではないでしょうか。併せて伺います。
3.大阪府の治水対策について
- Q1)
昨年の秋の台風18号の京都府や滋賀県での被害をみると、治水対策の重要性を改めて認識しているところであります。
大阪府では、平成22年に人命を守るということを基本理念に、「今後の治水対策の進め方」をまとめ、府民の皆さんに治水対策の取組効果を実感していただけるよう、今後20年から30年という期間で「防ぐ」「凌ぐ」「逃げる」対策を実施していくこととされています。
この進め方では、河川毎の洪水リスクを明らかにした上で、治水目標や治水手法を決めているとのことでありますが、一般の府民にとっては、現状の洪水リスクが30年先にどうなるのか、またこの間に、河川改修が実施されることや、調節地が設置されるといった程度はわかるかもしれませんが、30年というと、府民にとっては長い期間であります。
「今後の治水対策の進め方」が、府民の皆さんに治水対策の取組効果を実感していただくことを目標にしているのであれば、30年という期間の中で、どのように治水対策が進められていくのか、段階的に整備される施設の計画や効果についても府民に理解されることが重要であると考えます。
治水対策の進め方や取組効果を段階的に府民に対してわかりやすく示す必要があると考えますが、どうなのか、都市整備部長に伺います。 - Q2)
府の治水対策については、治水対策の進め方や取組効果が府民にわかりやすく示すことができるよう、しっかりと取り組んでほしいと思います。
一方、昨今のゲリラ豪雨のような局所的に大量の雨が短時間で降ると、府が、いくら地下河川や下水道増補幹線を整備しても、それらに雨水が流れ込む前に、市町村の下水管等で排水できずに浸水が発生する事例があります。
こうした課題への対応は、一義的には、市町村の役割であることは理解しますが、市町村においても、様々な課題を抱えていると聞いており、私の地元である枚方市においても、ゲリラ豪雨による浸水や汚水管渠の中に雨水が混じるような事例もあったと聞いています。
大阪府においても、市町村の抱える様々な課題に関する意見を聞きながら、内水浸水被害の軽減に向けて、市町村と連携して取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。
4.教育行政評価審議会について
- 教育委員会では、法律に基づき、毎年、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検・評価を行うに当たり、教育に関し専門的知見を有する外部の専門家で構成する審議会を設置し、調査審議をしてきたと聞いています。
今回、「大阪府附属機関条例」の改正が提案されており、その中では「大阪府教育行政評価審議会」を設置することとされています。
この審議会は、これまでの法律に基づく点検・評価に加え、昨年策定した大阪府教育振興基本計画の進捗状況を知事と教育委員会が点検・評価するに当たり、外部の専門家に調査審議していただくために設置すると聞いています。
昨年まで設置していた教育委員会の評価審議会では、義務教育、高校教育、支援教育など各分野の専門家を中心に、5名の外部の有識者を委員の任命し調査審議をお願いしてきたとのことでありますが、教育振興基本計画に掲げた目標を達成し、教育効果を上げていくためには、今回設置する審議会をより充実したものにしていく必要があります。
例えば、同じ専門分野の方々が複数入ってチェックする体制が必要であるとともに、部局からの提出資料だけを見るのでなく、委員が独自の視点からチェックすることが可能となるよう、より審査機能を強化し、客観性を高めていく必要があります。さらに、実際の運用において、審議会の重要な役割を委員にも十分に知っていただくためにも、審議会の位置づけや役割をもっと鮮明にしていく必要があります。そのためには、より一層強力な権限を付与することが不可欠です。その意味で、本当に審査していただく時間がこれで十分なのか、再度、考え直す必要があると考えますが、知事の考えをお聞かせください。
5.中国との経済交流と台湾との友好交流について
- Q1,2,3)
現在、我が国にとって最大の貿易相手国が中国であり、対中直接投資額は第2位、進出企業数は第1位となるなど、日中間の経済関係については、緊密かつ相互依存的とあるとされています。政府は経済面においても「戦略的互恵関係」を推進していくこととしているように、我が国と中国との間の経済交流は重要なものとなっています。
府では、昭和55年には、上海市との友好府市関係の樹立に関する議定書に署名して以来、経済、農業、医療、青少年交流をはじめとする広範な分野において友好交流事業を行っているほか、昭和60年には、府内企業が中国との貿易や企業進出時、情報提供等のサポートを行うことを目的に「上海事務所」を設置し、現在は名称を「大阪政府上海事務所」としています。橋下前知事も数度、中国への公費訪問を行っており、その成果についての検証が必要であることはいうまでもありません。
そこでまず、「大阪政府上海事務所」の活動内容、実績を踏まえた中国との経済交流について、商工労働部長に伺います。
また、近年、自治体外交が活発に展開されています。これは、自治体が独自に海外都市との間で姉妹都市提携や友好交流都市提携を進めるもので、国家による外交活動にない、自治体独自の特色が発揮できるものであり、まさにグローバル時代にふさわしく非常に意義深いものといえます。
府においても、これまでに友好提携を行っている海外自治体との間で相互理解を深めるために国際交流推進事業に取り組んでいますが、この事業の活動状況について、府民文化部長に伺います。
近年、中国は尖閣諸島を巡り、中華人民共和国の自国領土であるなどと根拠のない主張を繰り返し、その後現在に至るまで日中関係が冷却化したままの様相にあります。
一方、台湾は、外交関係がない中、我が国にとは外交関係がないとはいえ、我が国にとっては馴染みが深く、対日感情が良好であります。
将来を見据えたとき、橋下前知事のときのような場当たり的、短絡的な視野からの自治体外交を行うのではなく、近隣の友好諸国との間でしっかりとした、安定的・長期的な友好関係の維持・構築に努めるべきであります。
そこで、府として、経済交流と友好交流とを分けて考え、実のある独自の自治体外交を進めてもよいのではないでしょうか。府以外の自治体で台湾の地方自治体との間で友好交流事業を進めているところがあります。また、今後とも中国が我が国に対する批判を続け、我が国に対する態度を改めないような状況が続くようであれば、中国との友好提携を見直し、台湾の自治体との間で友好提携を行い、特に我々府議会日華親善議員連盟での活動を通じ議会同士で平成10年から交流が続いている台湾第二の都市である高雄市との間で友好交流事業を進めるべきと考えますが、知事の考えをお聞かせください。 - 要望)
ただ今、『緊密な関係を保てるよう』との答弁ですが、台湾との友好交流提携をより一層進めるべきであり、特に高雄市との間での友好交流提携を前向きに進めていただくよう要望しておきます。
6.淀川渡河橋の早期整備について【要望】
- 地元、枚方市を横断する計画の新名神高速道路については、平成35年度の全線整備に向け、昨年は地権者に対する説明会が開催され、設計協議用図面などの作成が進められているなど、大きく動き出しています。
昨年2月の定例府議会本会議において、私と同じ選挙区の中村議員が新名神高速道路に併設して淀川を渡河する橋梁の整備について質問を行ったところであり、このとき、府より、新名神の淀川を渡る部分は、ネクスコ西日本が鵜殿のヨシ原の環境保全に関する検討会において、環境保全に配慮した調査を今後3年程度かけた後、保全対策の検討を行い、橋梁設計や工事を行うと聞いており、併設橋については、淀川を渡る橋梁の一つとして、こういった新名神の検討スケジュールも念頭において、検討を進めていく、との答弁がありました。
淀川を渡河して対岸側とのアクセス向上を求めることは、地元枚方市の市民にとって、かねてよりの念願であります。
新名神高速道路の併設橋又は牧野高槻線の橋梁である(仮称)「淀川新大橋」のいずれの渡河橋も課題が存在するとはいえ、どちらかが整備されれば、枚方市内の渋滞緩和に一定の効果が期待でき、高槻市など近隣地域との交流促進に寄与するばかりか、地域活性化にも貢献し、防災面の機能強化にも大きな役割を果たし、極めて重要なネットワークを形成するものであります。
また、新名神高速道路の高槻インターチェンジへのアクセス道路となる、この淀川渡河橋は、今後、同インターチェンジの供用により、枚方大橋を補完する上でも重要な道路であることから、淀川渡河橋の整備を早急に図るよう、強く要望します。